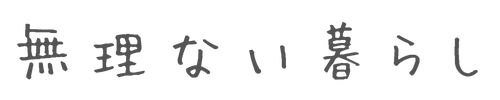Operatorのパラメーター
operatorのパラメーターの備忘録。他のシンセと違う所や気づいたところなどのメモ。自分用。
Operatorのセクションは大きく分けると4つ

三角を押すことで、中央に詳細情報が表示される。それぞれにセクションを選択すると、それに応じた情報が中央に表示される。
これを教科書として、Operatorが何と違うかを学習する。必要に応じて、記事を追加する。
1オシレーター
オシレーター AからDまである。音を作る部分
Coarseは基準になる周波数を整数で決定する。他のシンセではratio。Coarse2ならオクターブ上。Coarse4なら2オクターブ上。FMシンセとして使う場合は、モジュレーターのレベルを上げることで倍音の発生の仕方が決定する
どのような倍音が発生するかは、キャリアとモジュレーターの比によって決定される。

例えばAを選択すると、中央の詳細が開く。FM音源として使う場合は波形はサインのみしか選択できないのが一般的。Operatorは他の波形を使えることで、音作りの幅が広がっている。プリセットを確認する時に波形を確認すること。
A,B,C,Dの4つのオシレーターがあり、点灯させることでオシレーターを作動させる。
オシレーターにはエンベロープ・ジェネレーターがあり、これら2つをオペレータという単位で考えるのがFMシンセの基本。
DX7は6オペレータ。Operatorは4オペレーター。
追記︰2019/03/23
DX7では、フィードバックがオペレーター1つだけに掛けられる仕様だったが。Operatorはキャリアでないならフィードバックが掛けられるので、より複雑な倍音を作り出せる。
また、Velの値を高くすることで、ベロシティのアタックで音色変化が起こるように出来る。エレピで活用した。

比の特徴
- 1:1の場合 弦や金管っぽい音 ノコギリ波に近い
- 1:2の場合 クラリネットやハープみたいな音 矩形波に近い 奇数倍音
- 1:3の場合 オーボエや弦のような音 パルス波に近い
- 1:4の場合 クラリネットやハープのような音 奇数倍音
- 5以上 金属的
モジュレーターのレシオを少数を含むようにすると、非整数の倍音を発生する。デチューンサウンドを作れる。
Robert Henkeさんのやり方では、FMシンセの作り方だけれど、モジュレーターにノイズを持ってきて、アタックをつけるやり方をしていた。DX7とかでは出来ないOperatorのやり方なので覚えておく。
2 LFO

一定周期で、パラメーターを動かす。ピッチを動かせばビブラート、ボリュームを動かせばトレモロ。パンを動かせばオートパン。Operatorでは個別のオペレーターのピッチにLFOを掛けられる。フィルターにも。DestB(目的地、要するにLFOを掛けるところ)はボリュームやフィルターの他のパラメーターなどが調整できる。
アナログシンセと同じ
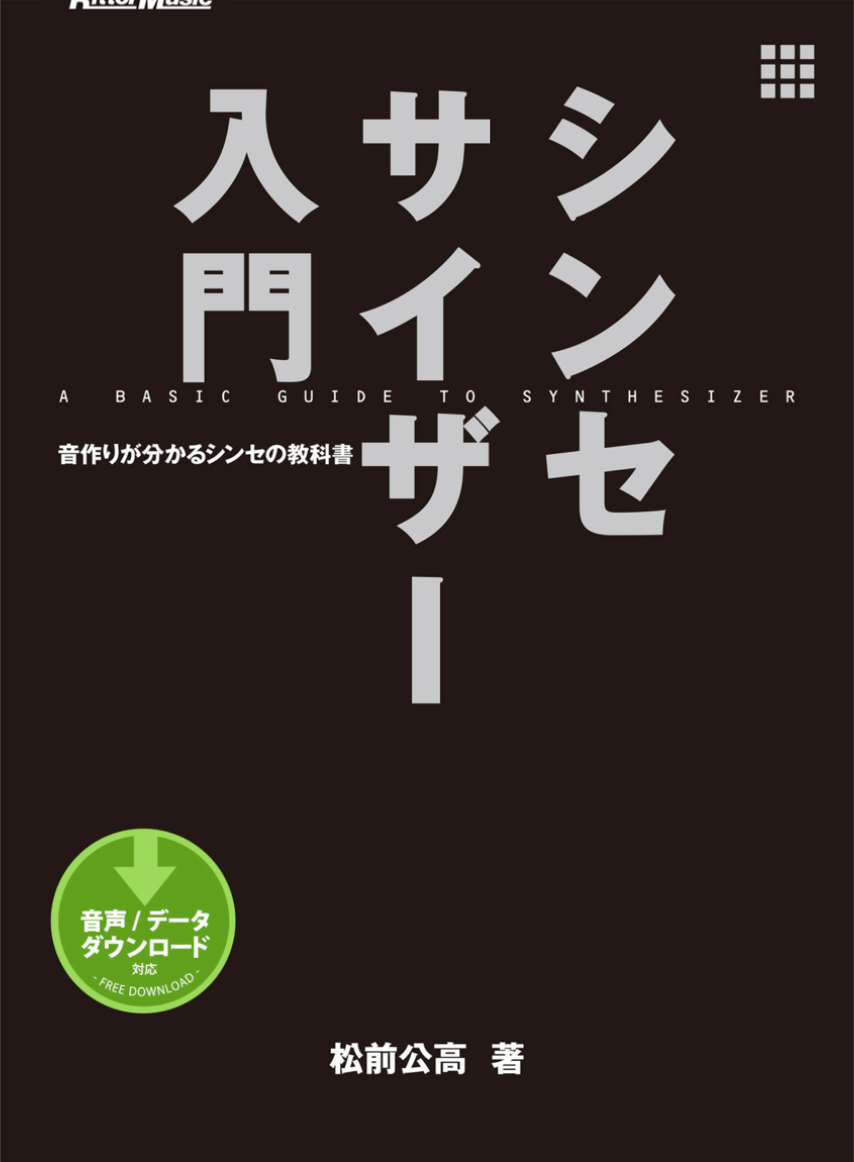
3フィルター

フィルター Operatorにはついている。フィルターの種類の選択、周波数、周波数を強調するレゾナンスがある。詳細メニューではフィルターのエンベロープ(時間的変化)、ベロシティでかかり具合を変化できたりする。
アナログシンセと同じ
FM音源ではついていないのも多い。
4 ピッチセクション

ピッチの時間的変化をコントロールするピッチエンベロープなどがコントロールできる。タムやキックの変化などで使う。
シンセベースで重要ななめらかに音をつなぐGlideなどはこちらでコントロールする。全体のピッチもこちらで調節。
Spreadはコーラス効果。オシレーターでデチューン(ピッチを微妙にずらす)ことをしなくても、こちらでコーラスを作れる。
追記:2019/03/23
spreadはFMピアノを作るのにも活用した。

ピッチエンベロープは、ドラムの音程変化などにも積極的に利用する。
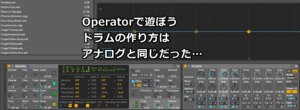
5 グローバルセクション

全体のボリューム調整や、ピッチベンド、アフタータッチなどの調整。重要なのは、アルゴリズムをここで設定すること。また、モノラルにする場合は、Voicesを1にすること。

一番シンプルなのは、アルゴリズムが直列になるパターン。オルガンなどは並列。
アルゴリズムの特徴などは理解するたびに追記。Ableton Liveのプリセットなどで比較してみる。