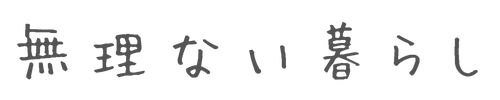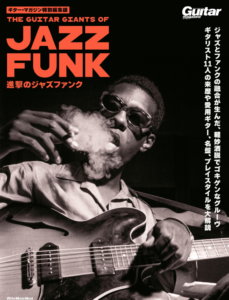いやあ、いつもながら頭が悪いタイトルですね…
ちょっと前に発売されたSoftubeのBluetoneがなかなかの反則だったので紹介します。
MULTI-MODE ENHANCERという謎の名前がついていてなんじゃコリャと思ったんですが、凄かったです。
下処理が難しいもの、これでやったら楽じゃないかな。負けた感があります…
TUBE-TECH BLUETONEとは
公式の文言を見ると、マルチバンドコンプとEQの組み合わせということで、プリセット集ですね。
マルチバンドコンプとEQはTube-TechのSMC 2BとTube-Tech Equalizers Mk IIを組み合わせたものとのことです。
TUBE-TECHの代表的な製品であるCL-1Bはボーカルに使ってもベースにも使ってもいい感じにしてくる反則的なコンプというイメージがあります。たいていのスタジオにあるように思います。
その反則的な製品を作るTUBE-TECHのマルチバンドコンプのSMC 2Bを使っているという。反則の匂いしかしない…
EQはPULTEC型のEQとして多分めちゃくちゃ人気があるだろうPE1C、ME1Bを組み合わせたTube-Tech Equalizers Mk IIということで、反則のオンパレードですね。
キックに使っても、ボーカルに使ってもいい。何をやってもいい感じになる反則EQと反則コンプを組み合わせた大反則プラグインという理解でいいんじゃないでしょうか。
いや、使うまでは、大したことないと思っていたんですが、凄かったのよ…
敗北した感があります。反則技に負けた。いや、完全に負けたとは思わないけれど、時短という意味では敗北ですね…
マルチバンド、難しいですしね。EQもちょっとやってあるくらいのお手軽プラグインでしょう。ふふん。お手並み拝見。GRみてEQしてというやつだから好みの感じにならないだろう。
まあ、デモで使って大したこと無かったらやめようと思っていたんですが、デモ期間も終わらないのに買ってしまいました…
また、Softubeに貢いでしまった…
プリセットから選んで微調整だけで使える状態になります。
悔しいからSoftubeのSMC 2BとTube-Tech Equalizers Mk IIを買って研究してこれよりいいもの作れるようにならないとな…
買う理由ができちゃった。仕方ないなあ。研究のためだからなあ。フフフ…
使い方
使い方も何もというくらいなシンプルなものですが、メモ代わりに書いておきます…

- プリセットを選びます
- AMOUNTを調整します。GRをみながら掛かり方をみて設定します。50%がうまくいくように設定されているので、音源によって調整ですね。GRがいい感じになるようにINPUTを調節しさえすれば、50%でも結構行けてしまうと思います。何だそりゃ…
- コンプ後のEQを調整します
- DRY/WETで潰し過ぎたらトランジェント戻したり、Makeupゲインを調整
これだけという。なんですけどね…
凄かったです…
ちょっと注意しておくとしたら、それぞれのプリセットがどういう目的で作られているかは理解しておくと、違うソースでも上手く使えるのではないかと。
思った以上にこれを起点にして出来てしまうということがわかりました。ハイパスがあるので音作りのバリエーションは見た目以上に多い。プリセットのバリエーションがいろいろあるので見ていきましょう。
プリセットの説明
マニュアルの文言を補足していきます。
Vocal Clarify 低域のコントロール、アーティキュレーションの強化、ディエッシング、ミックスの明瞭度を高め、マスキングを減らすイコライジング。
ディエッサーがあるということで、ちょっと耳が痛いようなパーカッションにも使えます。ローカットは入ってますね。痛いところは結構圧縮されるので、ボーカルでチョイスするならこれかなあ。ナレーションなんかにも使えてしまいますね。
Vocal Focus 高いレシオでよるハード・コンプレッション、デイエッシング、ミッドの強調。
ロックっぽいという印象を受けました。歌にも使えるけど、サックスに使ってもいい感じ。ガッツがある感じになります。
Mix Bus あらゆるミックスの中域のパンチを強化し、低域と高域を滑らかにする。
低域は結構圧縮してボワつかないようにしている感じですね。ホーンセクションに使ってもよかった。いろんな楽器のバスに使うとミックスが楽だと思います。
Mix Bus Wide ミックスのサウンドをワイドにし、中央部をよりクリーンにします。
使ってみました。簡単すぎる。ハイパスもあるので、低域引っかからないように使う事も出来ます。マスターに使ってもいい感じでした。この手のバスに使うもの、レイテンシーがかなりあるものが多いんですけど、脅威の4サンプル。
あとね、Dry/Wetがあるからノブこれだけしかないけれど、音作りの幅は大きいです。
制作とミックスを同時にするタイプの人には特に使いやすいと思います。私は、基本演奏して作るのでこの軽さはありがたい。Softubeの魅力でもあります。
初めはオフ。それからオンにしてます。
SoftubeのBlue Tone実験
— うりなみ (@urinami) June 15, 2024
まずはマスターに掛けた。ゲインマッチ簡単に出来るのとハイパスあるのはやっぱり便利。
マルチバンドコンプ+EQだけど、ほとんど何も考える必要がない。プリセット選んで、GRみて調整しただけ。
内部的には結構複雑なことやってるんだろうけど…
Dry/Wetあるのもいい。 pic.twitter.com/6olpTUuI81
Drum Bus あらゆるドラム・バスに接着剤を加え、箱鳴りを抑え、ミッドレンジにパンチを加える。
使ってみました。グルー感ありますね。打ち込み音源だからパツッとさせたけど、ふつうに生ドラム録音したらいい感じになるだろうと思います。打ち込みでも打ち込み臭さがなくなりますね。
中低域膨らんで他とぶつかりそうなところ、うまいこと処理してくれますね。結構気を使っていつもやっているところがこうサクッと出来るのは嬉しいんですけど、負けた感がありますね…
ドラムに実験。ここまでぱつっとさせることは自分はやらないけど手軽にできるのは便利。
— うりなみ (@urinami) June 15, 2024
他のプリセットでも応用はできる。素晴らしいと思ったのはやっぱり生楽器録音した時にさっと下処理終わるのは楽。
負けた感がある…
4サンプルはストレスがない。パフォーマンスで使えるレベルという。 pic.twitter.com/8uihkLUeWh
BASS INSTRUMENT 低域を均一化し、リッチでラグジュアリーなサウンドにし、中域に明瞭さを加える。
ベースのコンプは特に難しい。ボワついたり、ラインが見えにくくなったり、キックとの関係性もあるからEQもなかなか難渋するところなので、いろいろ勉強する必要があるパートですよね。
ですけど、もうEQもコンプもいいところにしてくれてあるので、GRと音質調整だけでそれなりのものが出来ちゃいます。ベースとボーカルは特に反則だった。粗く弾いたんですけど、これ一つでこうなっちゃうんですよ…
タッチ粗めのベースに掛けた。ゲインは合わせた。
— うりなみ (@urinami) June 15, 2024
低音のばらつきがなくなるので前に出てくる。ラインも見えやすい。
EQは6dbまでとなっているのだけれど、破綻しないので使いやすい。
今のチェーンのほうが感じは出るけど、手軽さは圧倒的だな…
多くの人はこっちのほうが好みだろう。 pic.twitter.com/K5BHL0ceVa
低音が安定して圧縮されているから、ボトムが薄い感じもしない。ラインもはっきり見える。前に出てきます。
Xだと音質悪くなるけれど、これでわかりますかね…
低音が安定してないと、ボーカルやらホーンやら他のパートのピッチが悪く聞こえたりすることあるから、ベースって異常に難しい楽器だなといつも思うんですけど、いい感じにしてくれてますね。
自分でも出来るけどさ。このスピードでは出来ないもんな。
もう、全部これでやってから微調整でいいんじゃという気になってきます…
今回、あえてダッキングしてないんですけど、キックもはっきり聞こえますね。マジです。
適切にEQしてあるのと、ベースの帯域とキックの帯域が上手く被らないようにプリセット作り込んであるんでしょうね。
マルチバンドコンプだから、下手にサイドチェインで雑にダッキングするよりうまくいく可能性すらある。
Softube,プリセットが異様に高品質なんですけど、どれも即戦力。ゲインをしっかり合わせさえすれば使えます。
これも中低域の基音が集まるあたりも上手に処理してありますね。エレピやスネアの下のところ、ギターや歌の太いところとぶつかるだろう。出来るかなと超上から目線で使ったんですけど、余裕で出来てますねえ…
EQやコンプ、全くわからないし、いい感じにならないという人はこれ使えばいいんじゃないかなあ。
私は細かくやりたいけど、微調整で満足行くものになっちゃいますねえ。
あ、これはベースという楽器の特性もあると思いますけど、GRをかなりしてもいい感じになると思います。動画では7dBでピークは10dBくらいゲインリダクションしてます。Dry/Wetがあるんで、トランジェント戻したかったらすぐ調節出来ますし。
追記:2024/06/26
なじまないホーンや打ち込み臭さの解消にFameとSunsetは素晴らしいですね… pic.twitter.com/ueH8ZQeU0l
— うりなみ (@urinami) June 25, 2024
ベース、ドラムバス、ホーン、鍵盤、左右のギターに使用。ギターはAmproom内と、バスでも使ってます。
エレピのみハイとローカット。ベースはノーEQです。プリセットでEQいじったのと、Amount調整しただけです。
これはベースは粗くは弾いてないので、それほどGRはしていませんけど、しっかりボトムが安定しますね。好みで微調整はするけれど、これでベースは出来ちゃいますね。普通のタッチです。
マスターはT-RacksのOneで調整してます。ベースはダッキングしてません。
追記:2024/07/15
ベース、ドラム、サックス、エレピ、ギター、コンガに。ベースはBlue Toneのみ。ノーEQ,ベースはダッキングしてません。
自分の好みよりモダン目に微調整しました。と言っても70年代半ばくらいのイメージですかね…まあ、フラットワウンドで弾いてるので、上は出ないです。巻き弦だともっとフレットノイズなどいい感じにしてくれるのでスラップなんかでもいいですね。
今までの例よりコンプは軽めにかけてます。ベースは軽めのタッチで弾いて軽く掛けてます。
3dBもGRしてないです。いい感じにしてくれますね。
Ableton12.1 オーディオでもMacro Variationsのレイアウトがあるのね。無茶できます。
— うりなみ (@urinami) July 3, 2024
PUSHの機能強化が非常に印象に残りました。
あと、Limiter思っていたより良いですね。RoarとLimiterをマスターに挿していろいろと。 pic.twitter.com/CtxBumjYtj
Keys/Guitar シンセ、ピアノ、ローズに接着剤と存在感を加えるだけでなく、アコースティックまたはエレクトリックのシングル・ギター・トラックにも使用できる。
Amp Room内でも使える。オクターブ奏法のギターに掛けた。整理された感がある。
— うりなみ (@urinami) June 15, 2024
Xでわかるだろうか…
リリースは変わっている。
びっくりしたのは、カッティングでもリードでもプリセットでいけることだ。
もう一方の刻みもBlue Toneを使っている。AmpRoomで使うと0サンプルになる。 pic.twitter.com/5S3hiTXQSm
Amproom内で使えるので、2つのギターに使ってみました。オクターブ奏法してる方はリリースの感じが変わってるのはわかリますけど、動画でわかるかな…
明らかにリッチな質感になって前に出る感じがありますね。
エレピにも使っているんですけどグルー感あります。
Amproom内で使うと脅威の0サンプルでした。
パフォーマンスで使えるレベルのレイテンシーなんですよね。PCベースの場合常にレイテンシーとの戦いになるわけですけど、そういう意味でもSoftubeはレイテンシーがどれも少ないのでおすすめです。
私は蛮族なので生演奏してストレスがないものが欲しい。そうなるとSoftubeばかりになりました。
Bluetone、Console1にも組み込めるし、Amproomに組み込めるのはびっくりした。
— うりなみ (@urinami) June 13, 2024
生楽器の録音だったらこれで大体下処理できちゃうんでは。
T-RacksのOneも素晴らしいけど、レイテンシーが結構あるので、4サンプルしかレイテンシーがないのは素晴らしい。負けた感があるな… pic.twitter.com/ufMAiAwYBO
さっきのだとカッティングの例がわかりにくいと思うのでこちらをご覧頂ければ。古い質感にしてありますけど、いい感じになってますね。
どういうことなんですかね?仕組みが謎すぎる…理屈分かる人いますかね…
なんでリードに使っているギターに使って成立するものが、カッティングで成り立つんや…と思ったんですけど、フォトセルに関係あるのかなあ。原理知りたいなあ…

ちゃんとトランジェントが鋭いものでもファンキーに聞こえるようになってるし、リードはリードでディケイ部分伸びてますもんねえ。
SMC-2Bの設定が知りたいです。本当にこの2つだけでやってるのかと思ってしまいますね…
Stereo Guitars Wide 左右のギターがハードにパンされたギター・バス用にデザインされ、サウンドをワイドにし、プレゼンスとハイエンドの明瞭さを加える。キーボード・サウンドにも効果的。
ヘッドフォンで聞かないとわからないかな…
— うりなみ (@urinami) June 15, 2024
STEREO GTRS.モードの実験
ギター2本で同じくらいの音量だと凄く広がった感があるのだけれど、エレピとEQで。
音量が違って音域も違うから、広がりを感じにくいソースでやってるけれど、聞き取りやすくなる。 pic.twitter.com/k0DVhZ3som
音量が同じようなギターだとはっきり効果がわかりやすいんですけど、意地悪して、音量も音域も違う刻んでいるギターとエレピをバスにまとめて使ってみましたけど、聞こえやすくなりますね…
ハードパンしているものを聞こえやすくという用途でも使えるはずです。

まとめ
他のトラックに戻ってEQしてということしてない。恐ろしいことに、今回シェイカーのみEQしましたけど、今回のトラック古い質感にしたもの、特に注がないのは全部ノーEQです。
そしてノーコンプです。ダッキングしていません。まあ、そもそもマルチバンドコンプとEQのプリセットなわけですけど、プリセットの微調整だけしかしてなくてこれという。どうなっとるのや…
ええっ?!てなりますよね。大反則プラグインということがおわかりいただけたんじゃないでしょうか。
全トラックBLUE TONE入れてやったんですけど、EQとしては、BLUE TONEの中のトレブルとベースいじっただけです。
ブースト・カットは6dBだけですから、トーンコントローラー的な働きのものです。破綻しない範囲でという範囲での設定ですね。
あくまで音色のコントロールだけと考えていいと思います。
Qが小さいんでしょうね。PULTEC型のEQでヌルっと掛かって気持ちいいです。
変な笑いが出てきますね。
いやあ、EQすら必要ないという。
AI系とは別の進化を遂げた異形のプラグインです…
Softube,Harmonicsも謎技術をぶち込んでくることありますからね。
見た目がアナログ的でわかりやすいし、音も好み。でもなんでそうなってるかわからないというのはあります。本当にこの2つなのかなあ…

意識するのは音色だけでミックスが出来る。大反則プラグインというのはこういうことです…
あ、嘘です。ごめんなさい。ハイパスがあるので、ローが引っかかりそうなところは使いました。

いやあ、ノーEQ,ノーコンプでこれが出来るというのは、反則にも程がある…
EQとコンプのプリセット集なんて、別に自分でやるからいいと思っていたんですけど、これだけ作り込まれていたらこのプリセットに価値がある。Softubeだと、Focusing EQと並ぶ反則プラグインだと思いました。

時間を掛けたら多分Tube-TechのSMC 2BとTube-Tech Equalizers Mk IIでやってること自分でも出来ると思うんですけど、圧倒的に速い。
大体自分でも気に入った設定が出来たらそこから微調整していることが多いですしね。
処理が難しいものはBLUE TONEをきっかけにやってみるのはありですね。でも、悔しいなあ。
Softubeでアナログごっこがはかどりますね!