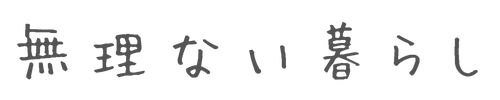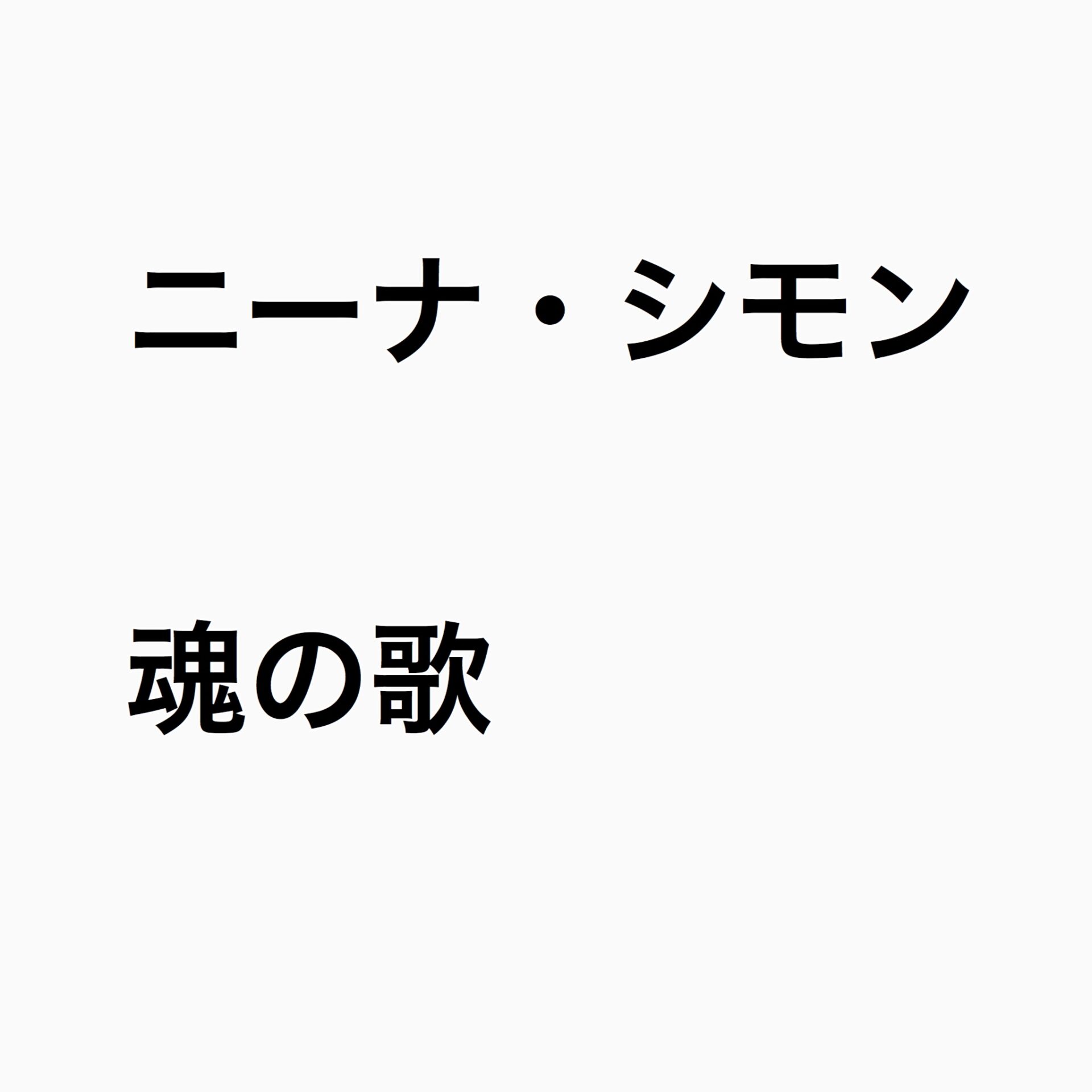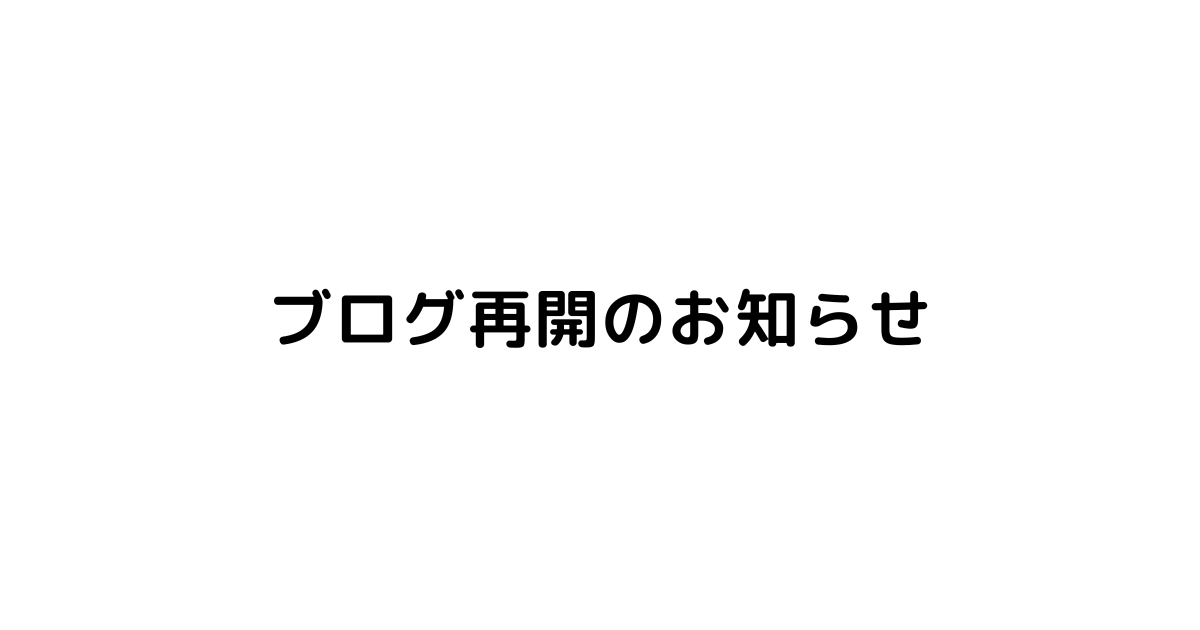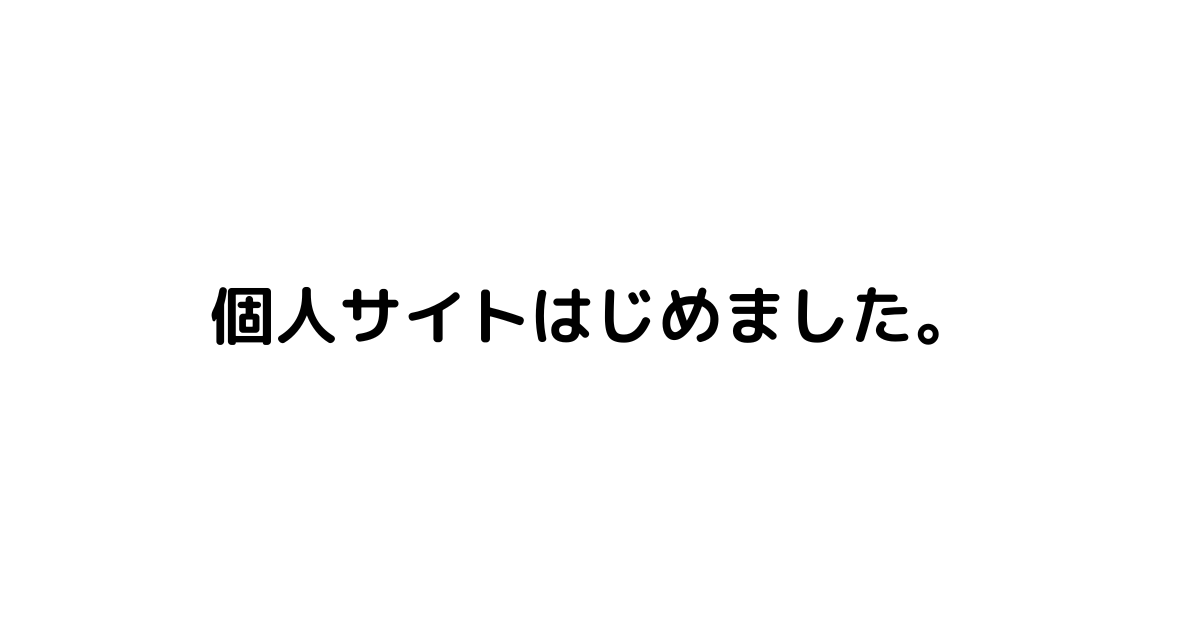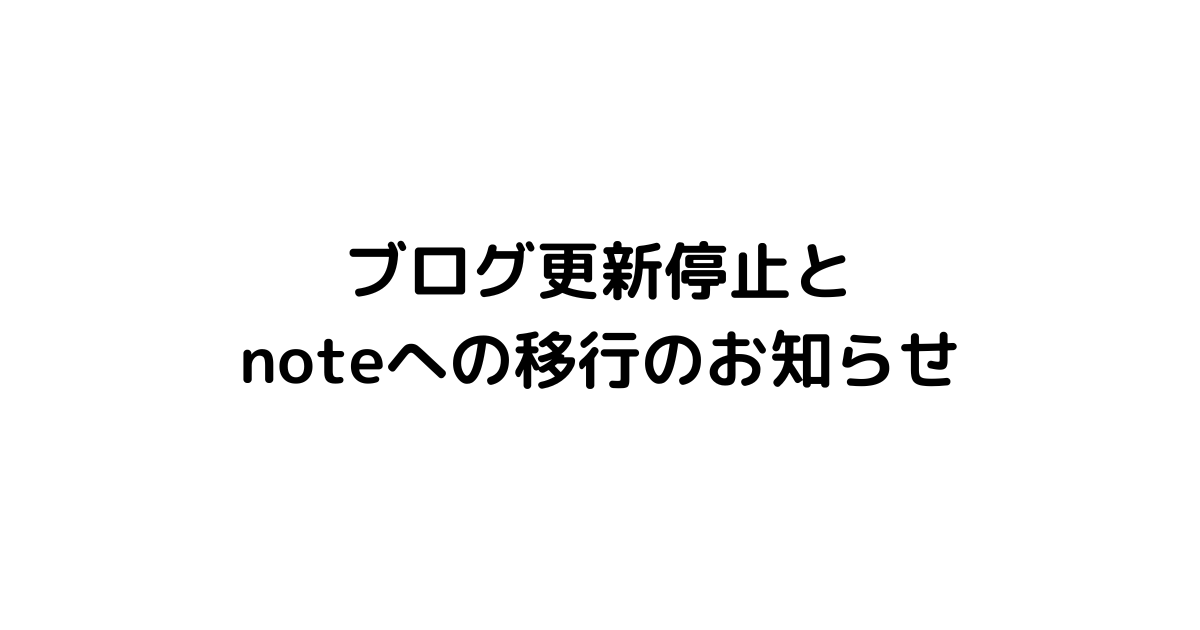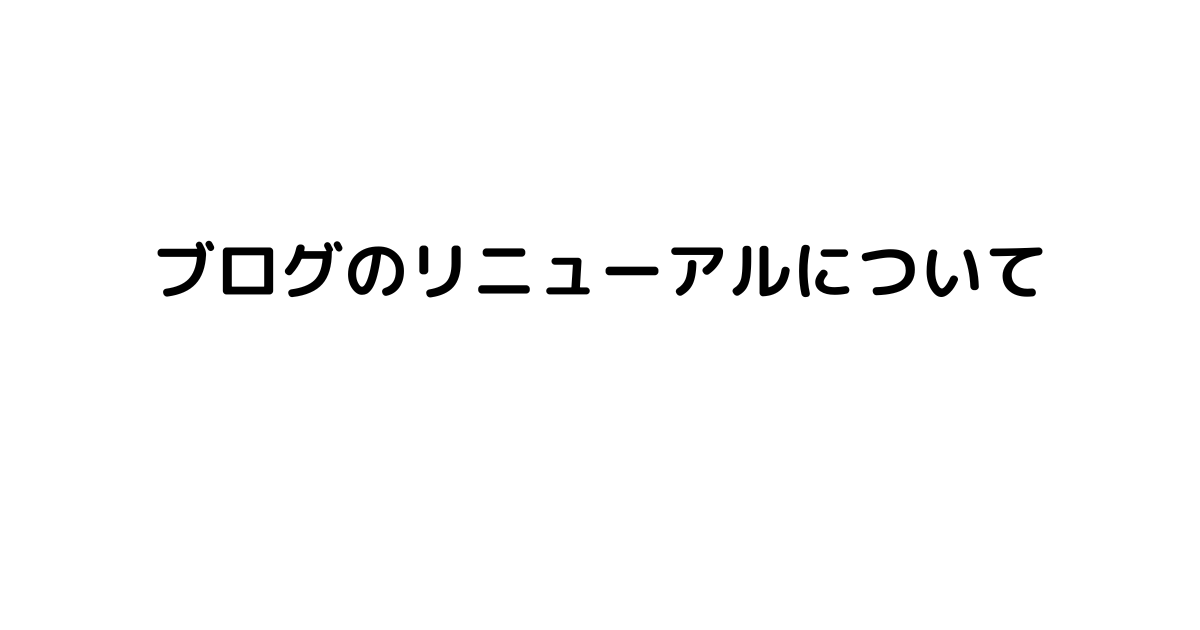ニーナ・シモン 魂の歌
ニーナ・シモン 魂の歌
家を離れている。寝付かれないので、NETFLIXでニーナ・シモンのドキュメンタリーを観た。
ニーナ・シモンは子供の頃から聴いてきた。メジャーのクリシェを覚えたのもニーナの曲だ。
子供にはニーナ・シモンの歌は恐ろしく聞こえた。
ニーナ・シモンがやっているものは、なんだとカテゴライズしにくい。歌っている内容はこの上なく黒人音楽と言える内容だ。けれど表現の仕方が全く異なる。
ピアノは、ジャズのプレイヤーとは全く違うので聴きなれなくて戸惑った。
非常にブルージーでソウルフルではあるのだけれど。
ニーナ・シモンがジュリアードに行ってから、歌い始めたのは何かのライナーだか雑誌で読んだ。
経済的な理由だったのか。
ニーナ・シモンがそれほどまでにクラシックでの成功を望んでいたとは知らなかった。
黒人という理由で、自分の夢を絶たれた怒りや絶望感は察するに余りある。
個人的な怒りから公民権運動にのめり込んで行くのは、当時のアメリカ社会で生きていたなら当然だったろう。
夫のDVもショッキングだった。思い出したのはティナ・ターナーとアレサだ。
自由、人間賛歌。そんなイメージと全く異なる凄惨な私生活。
時折引用されるニーナの日記も英語だともっと生々しい。
自由を歌っているのに、暴力に怯える日々。
自由とはなんですかと問うインタビュアーに対して
「恐怖がないこと。」と答えるニーナには衝撃を受けた。
ニーナは最終的にメッセージ性を高めて、アメリカでの地位を失った。コマーシャルではなくなったと言うことだ。
活動期間に穴があるのは知っていたが、リベリアに行っていたのは知らなかった。
夫と離婚して、アメリカにも絶望して、リベリアで今度はニーナが娘に暴力を振るうようになる。
ドキュメンタリーでは娘さんが出演しているのだが、率直に語るのはたいへん苦しかったろう。
ニーナが双極性障害だとわかったのはかなり後のようだが、今だったら適切な治療がなされただろうか。
生きながら焼かれるような苦しみだったろう。
ニーナのその後の復活劇も描かれるのだが、演奏という面では、正直聞くのが辛い。
あんなにメッセージ性がある歌を歌わなければ良かったというのも、仕事がなくなり困窮すれば当然だ。
ニーナが闘っていたのは、社会であり、夫であり、自分自身だったのか。
怒りがなければ一歩たりとて進むことはできない。でも、その怒りは自分も焼き尽くす。
ニーナの有名な言葉にこういうものがある。
An artist’s duty, as far as I’m concerned, is to reflect the times. – Nina Simone
私に関する限り、アーティストの義務は時代を反映することよ。
個人的な思想と社会の思想が合致して、大きな力になった。
ニーナは時代を体現したが、それは個人としての幸せを意味しない。
彼女の音楽がただ、過激なだけのものだったら、今でも愛されて歌われてこないだろう。
普遍的な苦しみ。人間なら生きる上で誰もが避けて通れない痛みをニーナは代弁して歌っているように感じる。
生きる上で、何かから疎外されることはつきものだ。人によっては家庭は地獄であり、社会が地獄かもしれない。病気は自分自身から疎外されることかもしれない。
でも、ニーナがhairで歌ったように、奪われないものもあるのだ。
力強く生命を肯定する。
ニーナの歌は、自分に向けて語りかけてくるように感じる。自分を含めた多くの人間が励まされてきた。
自由は恐怖がないこと。そして自分自身を所有することだ。
自由について考えるとき、いつもニーナ・シモンのことを思う。自分の生きる杖となってくれた歌。
自由について、考えている。
Spotifyのリスト
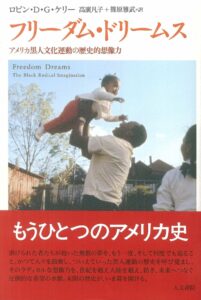
当時の状況も合わせて考えると、女性が公民権運動を行う内部でも差別を受けていたのだと読める。