ライブ配信では説明してきているのですが、長尺になるので記事を別にしました…
パッドで触りながら関連知識をまとめて速習したい場合はこちらの動画を御覧ください。
今回はダイアトニック・コードは3種類に分類できるよと言う話です。作曲、アドリブでもこの知識は使います。
ダイアトニック・コードについてはこちらに記事があります。
ここを押さえていたら大丈夫です。と言ってもそんなにむずかしいものではないので安心してください…
- 調性スケール(メジャー・スケール、マイナースケール)の音から3度ずつ音を重ねて作られるコードをダイアトニック・コードという
- ダイアトニック・コードはトニック、サブドミナント、ドミナントのいずれかになる。
トニック
トニックは、キーの主音をルートとする主和音です。
どういうことか見てみましょう。
Key=C
Cメジャー・スケールの構成音は、C,D,E,F,G,A,B 一音ずつ飛ばすとこういうコードが作れますね。
| コード名 | ディグリー |
|---|---|
| Cmaj7 | Imaj7 |
| Dm7 | IIm7 |
| Em7 | IIIm7 |
| Fmaj7 | IVmaj7 |
| G7 | V7 |
| Am7 | VIm7 |
| Bø7 | VIIø7 |
ちなみにキーはCと言ったら、Cメジャーということですね。マイナーの場合のみCマイナーなどといいます。
| コード名 | ディグリー |
|---|---|
| Am7 | Im7 |
| Bm7(b5) | IIm7(b5) |
| Cmaj7 | bIIImaj7 |
| Dm7 | IVm7 |
| Em7 | Vm7 |
| Fmaj7 | bVImaj7 |
| G7 | bVII7 |
ディグリー表記は、メジャースケールを基準に考えます。bや#はローマ数字の前に書きます。コードネームとそこが違いますね…
このローマ数字表記のⅠに当たるコードをトニック・コードといいます。
キーの主音といったら、この場合はKey=CですからCの音になりますね。Key=Cと言われた場合は、Cメジャーのことを指します。
3和音ならC,4和音ならC△7 その他にもC6とかも仲間になります。友達たくさんですね…
Key=Amの場合は4和音ならAm7がトニックコードになりますね。
安定した響きを持っているコードです。だから、曲の終わりに来ることが多いんですね。
ブルースの場合はC△7ではなく、トニックはC7になります。ブルースは調性音楽の理論では説明出来ず、モードと考えたほうが理解しやすいと思うのですが、他と違うとざっくり掴んでおいていただければ…
サブドミナント(Ⅳ)
ドミナントにもトニックにも行く機能を持っています。
Ⅳ-Ⅰの進行は、「アーメン」のコード進行なのでご存じの方も多いのではないでしょうか。
Ⅰ-Ⅳの繰り返しなんかもポップスに多いですね。ゴスペルやソウルにも多いです。こういうの聞いたらわかりやすいですかね…これはメジャーキーの場合です。
ライブ配信の補足です。
— うりなみ (@urinami) December 17, 2023
説明した特徴を適用させてトニックとサブドミナントのバンプを作ってみました。
まあ人間がやるほうが簡単なんですけど…
ギター、ベースは生楽器、ドラムは打ち込みました。鍵盤はPUSHで。知ってるだけで出来ることは結構あるのわかるんじゃないでしょうか… pic.twitter.com/iVGz9h9e6X
マイナーだとⅣm-Imという進行ですね。サブドミナント・マイナーと呼ばれます。
ドミナント(Ⅴ7)
ドミナントは、安定したトニックに戻りたい性質があります。(正確に言うと完全5度下=完全度4度上)
このⅤ7からトニックにいく動きをドミナント・モーションといいます。メジャーキーだとG7-Cのような流れですね。
まあ、ブルースは例外でドミナントからサブドミナントに行ったりします。ブラックミュージックやる人は全く気にしてないですね。あんまりこういう機能って、代理コード以外は意識しないです。
拡大解釈に次ぐ拡大解釈。現実世界なら怒られが発生するかもしれませんが、音楽の世界では問題ないです。楽しみましょう…
あんまりこういう機能って、代理コード以外は意識しないです。
何でドミナントモーションが強い動きなのか。トライトーンがあるから
増4度という音程を持っているからです。コードの3度と7度が増4度という関係にあるからですね。ちょっと、C7で考えてみましょう。
EからAまでの音程は4度、Bbだから増4度になりますね。
手形で覚えたら一発でわかりますね。動画で確認してください。

ライブ配信のときに、音程の協和度は物理に基づいていると言う話をしました。ある音程(音と音の距離)の比率を見るとわかりますね。
12の音程の中で最も協和度が低いのは短2度の15:16です。次に協和度が低いのが増4度音程の32:45となります。
だから安定してないように聞こえるわけです。人間の耳はかなり数学的で面白いですね。
実用的に使う時に大事なのは、V7の3度と7度の音、Ⅶm7b5のRと減5度は増4度の関係にあるって理解すればいいですね。この場合はBとFで斜めになってますからすぐわかりますね。
| コードネーム | CM7 | Dm7 | Em7 | FM7 | G7 | Am7 | Bm7(b5) |
| 構成音 | C,E,G,B | D,F,A,C | E,G,B,D | F,A,C,E | G,B,D,F | A,C,E,G | B,D,F,A |
| 構成音を度数で表すと | R,3,5,M7 | R,m3,5,7 | R,m3,5,7 | R,3,5,M7 | R,3,5,7 | R,m3,5,7 | R,m3,b5,7 |
| ローマ数字表記 | Ⅰ△7 | Ⅱm7 | Ⅲm7 | Ⅳ△7 | Ⅴ7 | Ⅵm7 | Ⅶm(b5) |
この増4度はトライトーンとも読まれる。トライって3って意味がありますよね。トライアングル、三角形ですよね。
もう一回、手形見を見てください。3度から7度までの距離、全音3つ分ありますね。だからトライトーンって言います。
完全5度へのルートモーション
もう一つの理由は、ベースが完全5度下、もしくは4度上(Gを1として、メジャー・スケールでCまで下がると5つやろ。もしくはGを1として、Cまで上がると4つやろ)にいく動きはめちゃくちゃ強いんです。
G7-Cというドミナント・モーションを考えてみることにしましょうか。


ピアノロールもつけておきます。

このトライトーンのBとFは、次にトニックのCとEに解決している。このトニックへの二つの半音の解決が強い解決を生み出しています。
G7ーCは4度進行を持っとる上に、さっきやった二つの半音の解決を持っている。
だから解決感が強いわけですね。このピアノロールや手形では、CはCがベースになってないですけど、アンサンブルではベースが弾いてるわけですから、4度進行と考えてください。
ジャズ・ポップス理論では転回型もコードが同じだったら機能は同じやろと考えるんですね。アバウトなんです…
ちなみに、ジャズやポップスでアホみたいに使われるⅡm7-Ⅴ7-Ⅰ△7は全部4度上に行っている進行だから強い進行ですね。そりゃよく使われるのがわかりますね。
そして、Ⅴ7-Ⅰというのはドミナントモーションです。これはSD-D-Tと機能的には考えられますね。3つ全部入っている。ラーメンのトッピングの全部盛りみたいなもんですかね。こういうこと書くとまた怒られが発生するかもしれません…
フル・ケイデンスと言ったりしますけど、別に覚えなくても問題はないです…
分析するときに知っていると便利ですけどね。
マイナーの場合は?
| コード名 | ディグリー |
|---|---|
| Am7 | Im7 |
| Bm7(b5) | IIm7(b5) |
| Cmaj7 | bIIImaj7 |
| Dm7 | IVm7 |
| Em7 | Vm7 |
| Fmaj7 | bVImaj7 |
| G7 | bVII7 |
ナチュラルマイナーで考えると、え、ドミナントコードって5番目のコードじゃなかったの?G7はあるけどこれだとトニックのCmaj7にいって、トニックのAm7に解決しないやん。もう嫌や…絶望しますね…
大丈夫です!そうやって考えられる人は理詰めに考えられるということですよ。
Em7って、構成音を考えると、トライトーンを持っていません。
ですから、不安定じゃないからトニックに戻る力が弱いんですね。なので、トライトーンを作るために、Em7のE,G,B,Dの構成音のGをG#にします。そうするとE7になってトライトーンが生まれる。
このG#を作るために、ハーモニック・マイナー・スケールは生まれるわけですね。
だから、ドミナント・モーションがメジャーかマイナーを決定します。
CメジャーとAマイナーは同じですよね。だって、構成音は同じですからね…
平行調の場合は、プレイヤーはメジャー、マイナーを意識しない人も多いと思います。そのほうが実用的ですしね。
5度がマイナーの場合は、ドミナント・マイナーと言ったりすることもあります。古いゴスペルなんかだとよくありますね。今のR&Bでも普通に出ては来ますけれど…
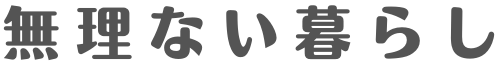


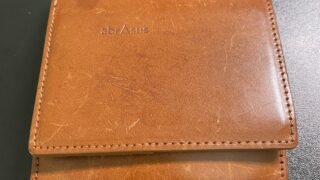



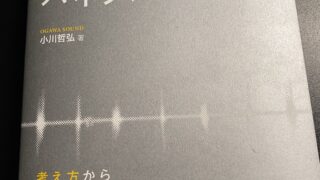



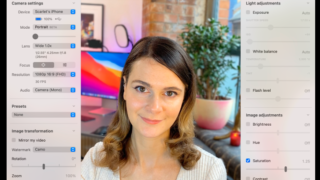





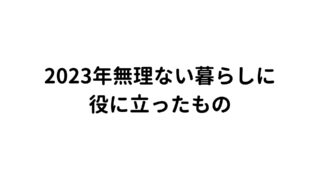













コメント